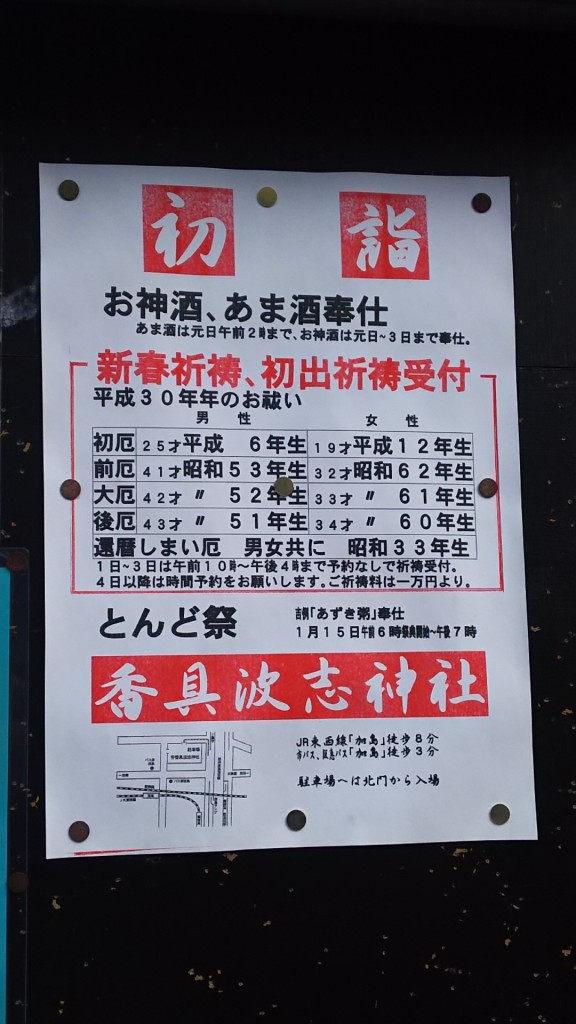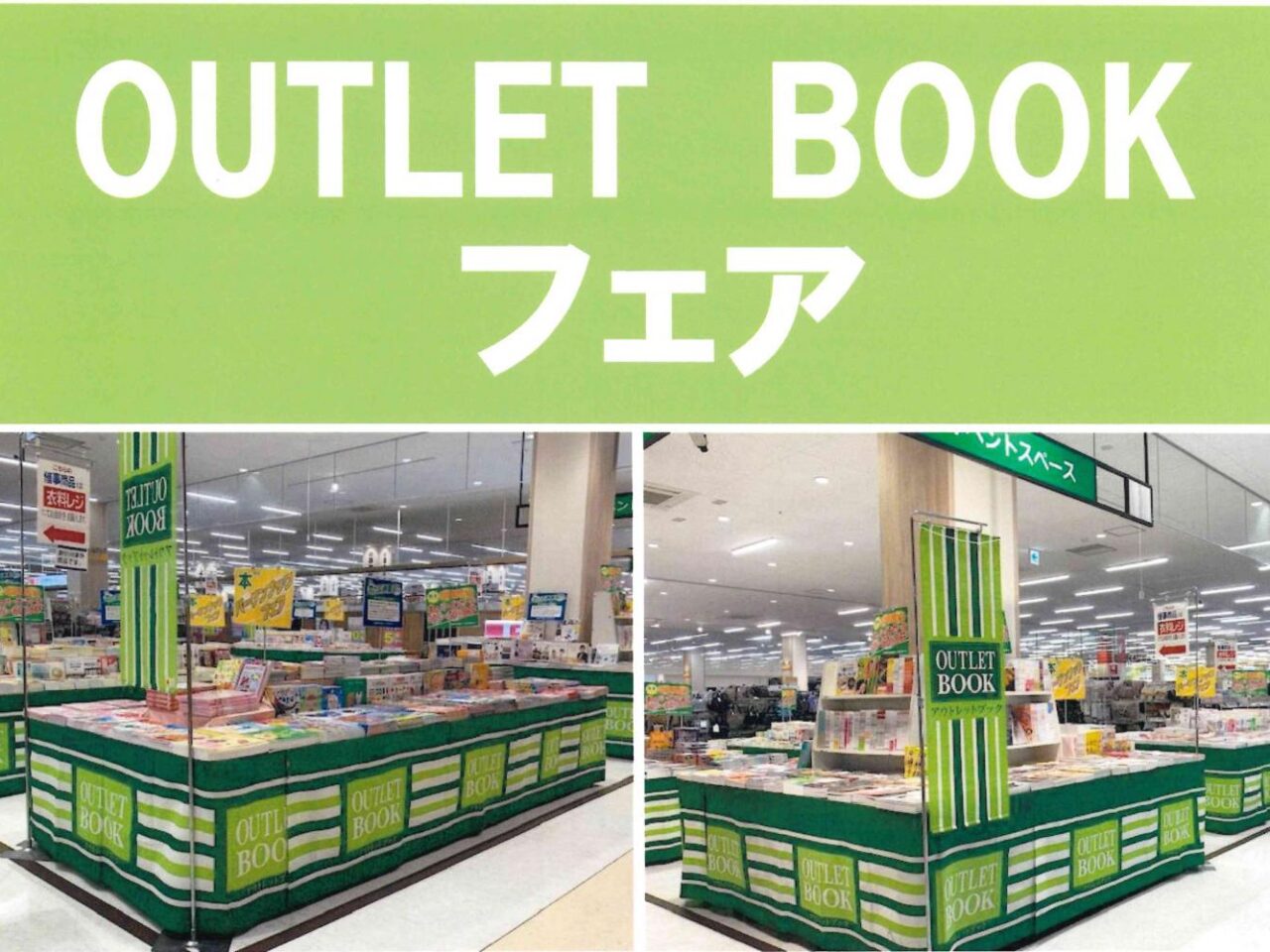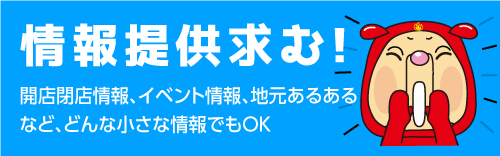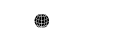【淀川区】初詣の後は、《とんど祭》が香具波志神社で行われます! 子どもに聞かれて困ったことありませんか? 日本の行事について、調べてみました。
1月15日は《小正月》ですね。
ここを過ぎると、やっと正月気分も終わって、ちゃんと日常生活に戻らないといけないなー。という気分になります。
小正月は元旦のように、初詣のような行事があるの?
と疑問に思ったので、日本人に生まれながらも、あまり知らない日本の行事を調べてみました。
地域性が強いので、細かな日数や日程は、地域・習慣によりけりな部分が多数あります。ご容赦くださいね。
1月1日は、元旦です。
門松やしめ縄、お鏡餅を飾って、お祝いしますが、このお祝いは誰のため?
簡単に言うと、全て《神様》のためです。
門松は、年神様が年始に地上に降りてくる際、『大掃除も済んで、神さまをお迎えする準備が整いました。どうぞお越しください。』とお伝えする目印だったそうです。
大掃除やおせち料理、お鏡餅の準備など、年越しの準備が完了して、一番最後に取り掛かるのがよさそうですね。
(写真はイメージです)
しめ縄の起源は、天照大神の『天岩戸隠れ』に由来するようです。
弟 素戔嗚尊(すさのおのみこと)の横暴に怒って、岩戸に隠れてしまった天照大神が出てきた際に、二度と岩戸に隠れられることの無いように、岩戸にしめ縄を巻いて、岩戸が開かないようにしたのが始まりのようです。
年始にお越し頂いた年神様を松の内と呼ばれる1月15日まで(地域によっては1月7日まで)の間、帰さないためでしょうか?
(写真はイメージです)
鏡餅はなぜ『鏡』餅なのでしょうか?
まん丸いお餅と、現代の平べったい鏡は似ても似つかないものですが、鏡が青銅でできていたころは、こんな形だったそうです。
では、飾った鏡餅はどうなるのでしょう? こちらは、松の内とは異なり、《鏡開き》と言って、別の日程で行われます。
関東と関西では、徳川家光の月命日の兼ね合いもあり、大きく異なるようですが、関西では、1月20日が主流のようです。
その他、1月4日や1月11日に実施されるところもあるそうですが、開いたお餅は、神さまのお下がりとして、ありがたく頂くので、今回は細かく触れないことにします。
松の内まで飾ったお正月のお飾りは、飾った後はどうしたらいいのでしょうか?
ようやく本題です!
年神様をお迎えするという1つ目の大役を果たしたお正月飾りは、神社で1月15日に《とんど祭》の際に燃やされます。
ここで2つ目の大役、年神様と一緒に、けむりとなって、天へ帰る。ということを果たすのです。
小正月に行われる《とんど祭》は、年神様をお送りするという意味があるのですね。
また《とんど焼きの火》に当たると、その年1年は健康でいられる。といういわれもあるそうです。
《香具波志神社》でもとんど祭が行われます。
午前6時から祭典が始まり、19時まで《あずき粥》がふるまわれるそうです。
今年厄年だけど、まだ厄払いの祈祷を受けていらっしゃらない方、まだ厄年かどうかの確認すらされていらっしゃらない方は、重ねてご確認くださいね。
当日、時間が取れない方は、事前に、また後日でも、お正月飾りを受け付けていただけるかもしれませんので、直接、神社にご確認くださいね。
日本の伝統行事を再確認・再認識し、皆さまが素敵な一年を送られることをお祈りいたしております。
↓ 《とんど祭》が行われる『香具波志神社』はこちら
住所:淀川区加島4丁目4-20 電話番号:06-6301-6501
[map]淀川区加島4丁目4-20[/map]
【けとし】
【注目!!】淀川区のクーポンてんこもり
「ゴーガイチケット1月号」はこちらから!